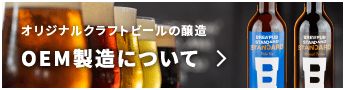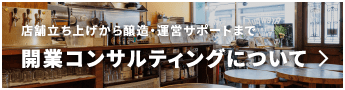2014.08.11BLOG
2014/8/11 クラフトビールとは何か

かなり大きな題目だなぁ。
ずいぶん前に書きかけた記事、公開するのを忘れてたっぽい。笑
3月に書いてるわ。一応アップしとこう。
クラフトビールってビールの一ジャンルになるのかな。
それとも日本人のいう「ビール」とは違うものを目指そうとしているのか。
これ書いたとき(今でもそう変わってないが)今のクラフトビールのあり方にかなり悲観的。
改めて読むとちょっと喧嘩売りすぎな気もする。笑
関西の酒蔵ブルワリー三社合同で行われる協議に参加してきた。
うち以外はかなり大きなメーカーで、コンサルタントの先生にアドバイスをもらいながら進める話し合いでなかなか考えさせられる話題に。
まず、クラフトビールとは何か?
これ、意外と答えられません。
業界的な認識でいえば、国内でいえば大手四社(オリオンいれて五社)以外のビール。
でもこれって全然、クラフトビールそのものを表してない。
小規模であればそれだけでクラフトビールなのか?
そもそも、大手以外のビールを「地ビール」として打ち出してきた歴史があって、地ビールのイメージが悪くなってきたから地ビールを捨ててクラフトビールとして再出発したわけです。
クラフトビールが流行ってると思ってるのはその業界にいる人と、全体のシェアのうちの1%でしかないファンの人たち。
残りの99%の人からすればクラフトビールと地ビールを分ける基準はかなり曖昧で、だかこそ身内だけでしか商売になってない。
一応アメリカのクラフトビールの基準は、小規模・独立的・伝統的製法、というこれまた日本には合致しなさそうな基準です。
結局クラフトビールってなんなんだ。流行ってる流行ってるっていってるものなのに、誰もうまく説明できない。ビアパブ関係者やメーカーでさえはっきり定義できないものを、どうやって一般の人に説明して理解してもらえるだろう。
ここが正念場な気がします。
大手ビール=ピルスナー
それ以外のビール=100種類を超えるスタイルのビールのすべて
こういう始め方をすると、説明しようったって無理だ。なんか根本的な誤りを犯してる気がする。
クラフトビールを、大手ビールと違うものって区切っちゃうからややこしくなるんじゃないだろうか。
日本のビール=大手ピルスナーっていう前提があるから、クラフトビールは日本のビールじゃないような感じになる。ビールっていう商品の中にピルスナーもクラフトビールもあるべき。
クラフトビールはうまい。日本人が今まで知らない味わいで、それが強みだと業界の人たちは思ってる。
じゃあなんでこんなにも広がらないんだろう。
クラフトビールには、小難しさや分かりにくさがある。
メーカーやビアパブは、大手ビールのピルスナーと何がどう違うのか、違うから何がすごいのか、うまいのか、それをお客さんに説明して教育するところからやらなきゃいけないと思ってる。と思う。
そんなのは、お客さんからしたら迷惑な話で、だからいつまでたっても広がらない。
クラフトビールって単語がもっと単純明快で魅力的に感じられるイメージを持たないと、いつまでたってもシェアは1%にとどまりそうだ。
エールという言葉でさえ一般的とはいえない。一般的にも感覚的にわかりやすい体系化されたビールのスタイル別のカテゴリーさえないように思う。実際、ブルワー同士で集まって話ても、100%直感的に理解できるカテゴライズってできなかった。
一般的な官僚は、クラフトビールは成長産業じゃないと思ってる。そりゃそうだ。20年やってもまったく伸びてない。
だから、税制を優遇したり緩和して守ったところで大した意味はないと思ってる。
きっとビールの税制は変わらないだろう。
日本のクラフトビール業界は全然明るいわけじゃない。
ここまで書きかけだったわけですが、どこにオチを持って行きたかったのか覚えてない。笑
たぶん、だからこそブルーパブがおもしろいんじゃないか、
という話になる予定だと思うんだけど。
最近は思うのは、ビールの作り方だけ勉強してもだめなんじゃないかということ。
コストを抑えて自分の思うビールを作るための、場所・設備の設計やマネジメントの能力も必要だろうと。
仕込みと発酵管理において、どの行程にこだわるべきで、どこに投資しないと品質が保てないのか、今の知識じゃまだわからない。
これは経験も必要だと思うけど、多くのブルワーは一つの醸造所、1つの設備に慣熟してそれに合わせて製品を造るから、設備が変わるとまたそれに合わせて工程のポイントをさぐっていかなきゃいけない。と思う。ここはセンスも問われる気がするなぁ。
というわけで最近は、具体的に醸造設備をどうやって構築するか、を考えてます。
会社の倉庫にゴロゴロ転がってる小型のタンクやら仕込釜を想定に入れて、それでやるならどういう設計にするのがベターか、というシュミレーション。
釜やタンクは、必要ってわかりやすいんだけど、
考えていくと、マッシュやウォートの移送はどうしよう、とか、冷却はどういう方式にすべきか、とか、発酵で温度管理はどうするか、貯酒とパッケージングとサービングをどうやってまとめようか、とか。
サニタリーやメンテナンスまで考えたらもっと複雑になりそうだ。うーん。
飲食スペースまで考えて一緒に構築していかないと、無駄も出てきそうだし、、、これがビジネスモデルとしてまとめられたらめっちゃおもしろいと思うんだけどな!
という妄想の日々です。